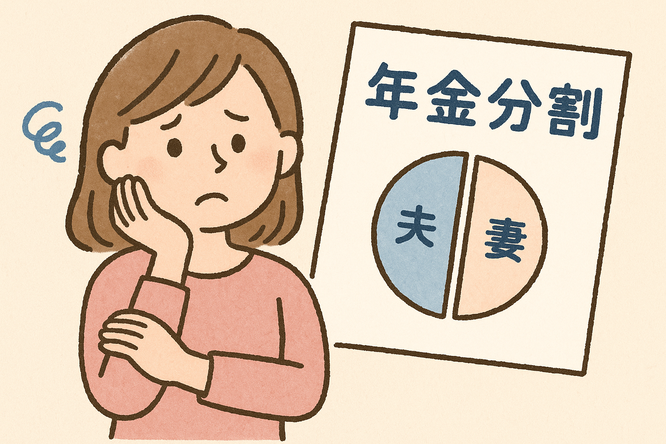
「結婚生活を支えてきたけれど、もし将来、別々の道を歩むことになったら…」
「私は扶養内で働いていたけれど、年金ってどうなるんだろう?」
「将来、年金ってどうなるの?」
そんな疑問を持つ方は多いと思います。
とくに、パートや短時間勤務などで家庭と仕事を両立してきた方にとって、
“老後の年金がどれくらいもらえるのか”は、とても気になるテーマです。
実は、結婚しているあいだに夫婦で築いた厚生年金の記録を分けられる制度があるのをご存じですか?
それが「年金分割制度」です。
これは、夫婦が協力して築いた年金記録を、離婚後に公平に分ける仕組み。
家事や育児、パートなど、家庭を支えた時間もきちんと評価してくれる制度なんです。
この制度を知っておくだけで、将来の年金を自分の力で守る第一歩になります。
これは「夫の年金をもらう制度」ではなく、
「家庭を支えたあなたの努力を年金に反映する制度」です。
1.年金分割制度には2つの種類があります
「年金分割制度」とは、結婚していた期間に夫婦で築いた厚生年金の記録(収入に基づくデータ)を分け合う仕組みです。
たとえば、
- 夫がフルタイムで働いていた
- 妻はパートで扶養内(第3号被保険者)だった
というような場合、
夫の年金記録(=将来の年金額のもとになる情報)を、婚姻期間中の分について“半分ずつ”にして反映できます。
この制度が作られた理由
この制度の背景には、「家庭を支えてきた人も、将来の年金で不利にならないように」という考え方があります。
以前は、会社員や公務員など厚生年金に加入していた側(主に夫)にしか年金記録がつかない仕組みでした。
しかし、2007年・2008年の制度改正により、婚姻期間中の年金記録を分けられるようになったのです。
つまり、「一緒に家庭を築いた期間の年金は、2人のもの」と考えられるようになったわけですね。
家事や育児、パート勤務なども立派な「社会的貢献」です。
年金分割は、その努力を将来の年金にもきちんと反映させるための制度です。
| 制度名 | 内容 | 対象になる人 |
|
①合意分割制度 (2007年4月〜) |
結婚中の厚生年金を、話し合いや裁判で 決めた割合で分ける制度 |
共働き夫婦・どちらも厚生年金に入っていた人 |
|
②3号分割制度 (2008年4月〜) |
夫が厚生年金加入者で、妻が扶養内 (第3号被保険者)だった期間を自動で半分に分ける制度 |
パート勤務や短時間勤務で夫の扶養だった人 |
「パートで働いていたけど社会保険は夫の扶養だった」という方は、この②3号分割制度の対象になることが多いです。
2.手続きの流れと気をつけたいポイント
「年金分割」と聞くと、難しそうな印象を受けますよね。
でも実際の流れは、とてもシンプルです。
次の3つのステップを順番に進めるだけでOKです。
✅ステップ①:「情報通知書」をもらう
まず最初にすることは、自分の年金の情報を確認することです。
年金事務所で「年金分割のための情報提供請求書」を出すと、婚姻期間中の厚生年金の記録がわかる「情報通知書」が届きます。
💬 ポイント
離婚前でももらえます。
早めに確認しておくことで、後から慌てることがなくなります。
✅ステップ②:分け方を決める
-
合意分割制度の場合
👉夫婦で話し合い、または家庭裁判所の調停・審判で割合を決めます。 -
3号分割制度の場合
👉合意や裁判は不要です。離婚後に自分から年金事務所へ請求するだけでOK。
💬 ポイント
分割割合は最大で「1/2(半分)」まで。
家庭を支えた期間の厚生年金の記録を公平に分けるイメージです。
✅ステップ③:年金事務所で請求する(離婚後2年以内)
離婚が成立したら、2年以内に年金事務所で請求します。
この期限を過ぎると、原則として分割できません。
📄 必要なもの
-
情報通知書
-
戸籍謄本(婚姻・離婚日がわかるもの)
-
本人確認書類(マイナンバーカードなど)
-
合意書や調停調書(合意分割のみ)
⚠️ ご注意!
期限を過ぎると原則として請求できません。
離婚後は生活の手続きが多いですが、「2年以内」という期限だけは忘れずにメモしておきましょう。
注意しておきたい3つのこと
1.分けられるのは厚生年金だけ
👉国民年金(老齢基礎年金)は分割の対象外
2.対象期間に注意!
👉3号分割制度が使えるのは、2008年4月以降の期間のみ
3.相手の同意がなくてもOKな場合がある
👉3号分割は配偶者の同意や署名は不要
あなた1人で年金事務所に請求できる
年金分割の手続きは、やってみると意外とシンプルです。
ただし、期限を過ぎてしまうと取り返しがつきません。
「情報通知書」を早めに取り寄せて、自分の年金記録と対象期間をチェックしておきましょう。
少しの準備で、将来の安心を確保できます。
年金のことは“老後の話”ではなく、“今の生活設計”の一部として考えていくことが大切です。
3.図で見る!年金分割のイメージ
年金分割のイメージを図で見てみましょう。
文章だけだと少しイメージしにくいですが、図にするととてもシンプルです
こうして、結婚中に夫婦が築いた厚生年金の記録を公平(1/2ずつ)に分けることができ、将来の年金額に反映される仕組みです。
💬 ひとこと
これは“もらえる金額を分ける”のではなく、
“将来の年金計算の基礎データ(標準報酬)を分ける”というイメージです。
「合意分割」と「3号分割」のちがい
| 比較項目 | 合意分割制度 | 3号分割制度 |
| 制度開始 | 2007年4月〜 | 2008年4月〜 |
| 対 象 者 | 共働きなど夫婦双方が厚生年金加入 | 夫が厚生年金、妻が扶養(パートなど) |
| 分 け 方 | 話し合いや裁判で決める(最大1/2) | 自動で半分ずつ(1/2) |
| 手 続 き | 合意書または裁判書類が必要 | 本人が年金事務所に請求するだけ |
| 期 限 | 離婚成立後2年以内 | 離婚成立後2年以内 |
こんな方が対象になります
- 結婚中、夫が会社員・公務員で厚生年金に加入していた
- 妻はパート勤務や扶養内で働いていた
- 婚姻期間中の年金記録を確認したい
- 離婚を考えている、または離婚後2年以内
💬 ひとこと
「私は扶養内だったから関係ない」と思っている方も、実はこの制度の対象になっていることが
多いです。
よくある誤解・注意点
| 誤解しやすい点 | 正しいポイント |
| ❓「離婚したら自動的に分けられる」 | → ✍ 自動ではなく、自分で年金事務所に請求が必要です。 |
| ❓「国民年金も分けられる」 | → ✍ 分割できるのは厚生年金部分のみです。 |
| ❓「昔の結婚期間も全部対象になる」 | → ✍ 3号分割の対象は2008年4月以降の期間のみです。 |
| ❓「夫の許可が必要」 | → ✍ 3号分割なら相手の同意は不要です。 |
4.まとめ
パートで働きながら家庭を支える時間も、立派な「社会の支え」です。
年金分割制度は、「老後の年金を公平に分け合う」ための制度で、その努力をきちんと評価してくれる大切な仕組みです。
💬 FPとしてのアドバイス
✅ 離婚後2年以内の請求期限を忘れない
✅ まずは「情報通知書」を取り寄せて確認
✅ 婚姻期間中の記録を確認し、自分が対象かをチェック
✅ 分からないときは、年金事務所や専門家に相談
制度を知っておくことが、将来の安心を守る第一歩です。
今からでも遅くありません。小さな行動が、あなたの老後を大きく支えてくれます。



