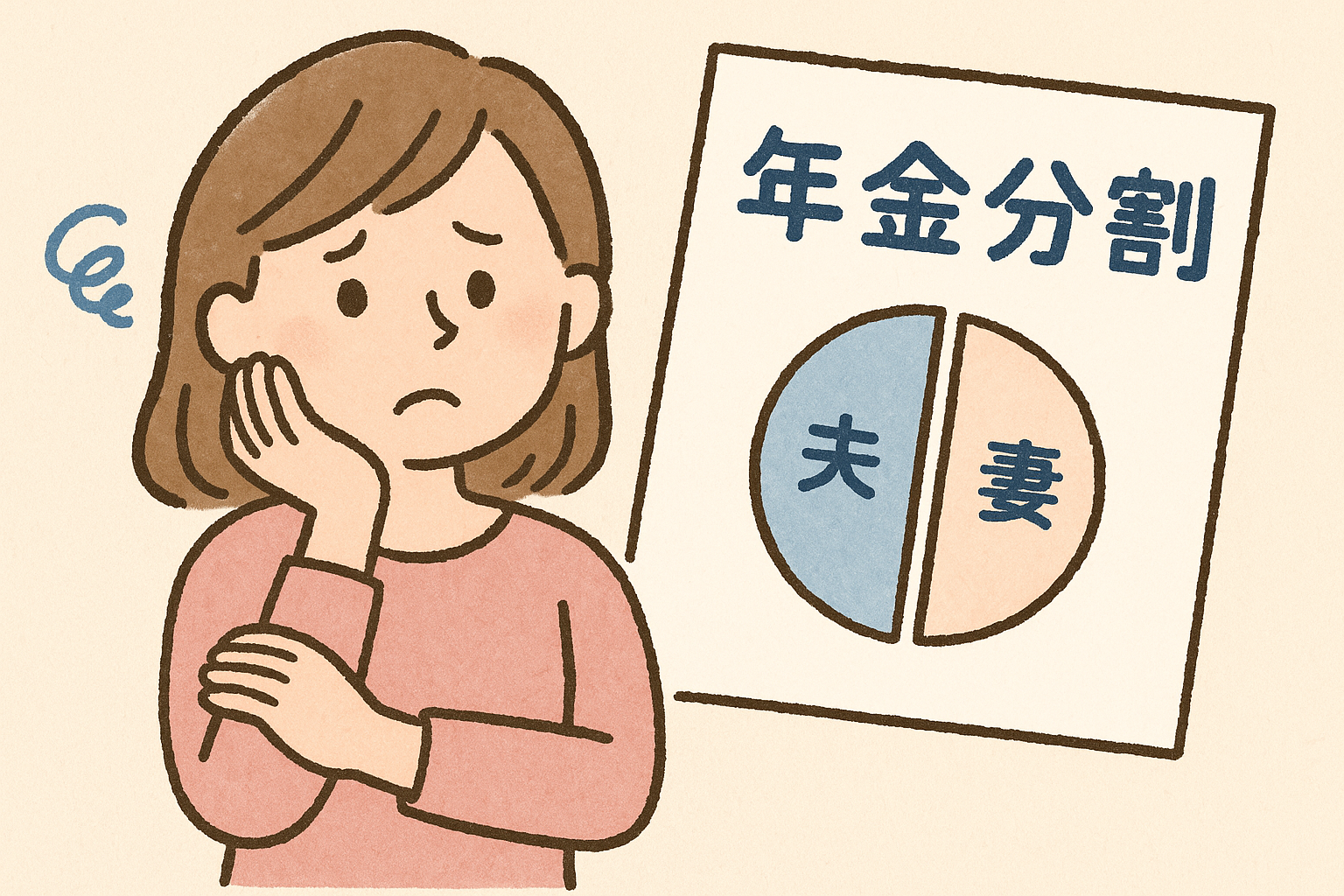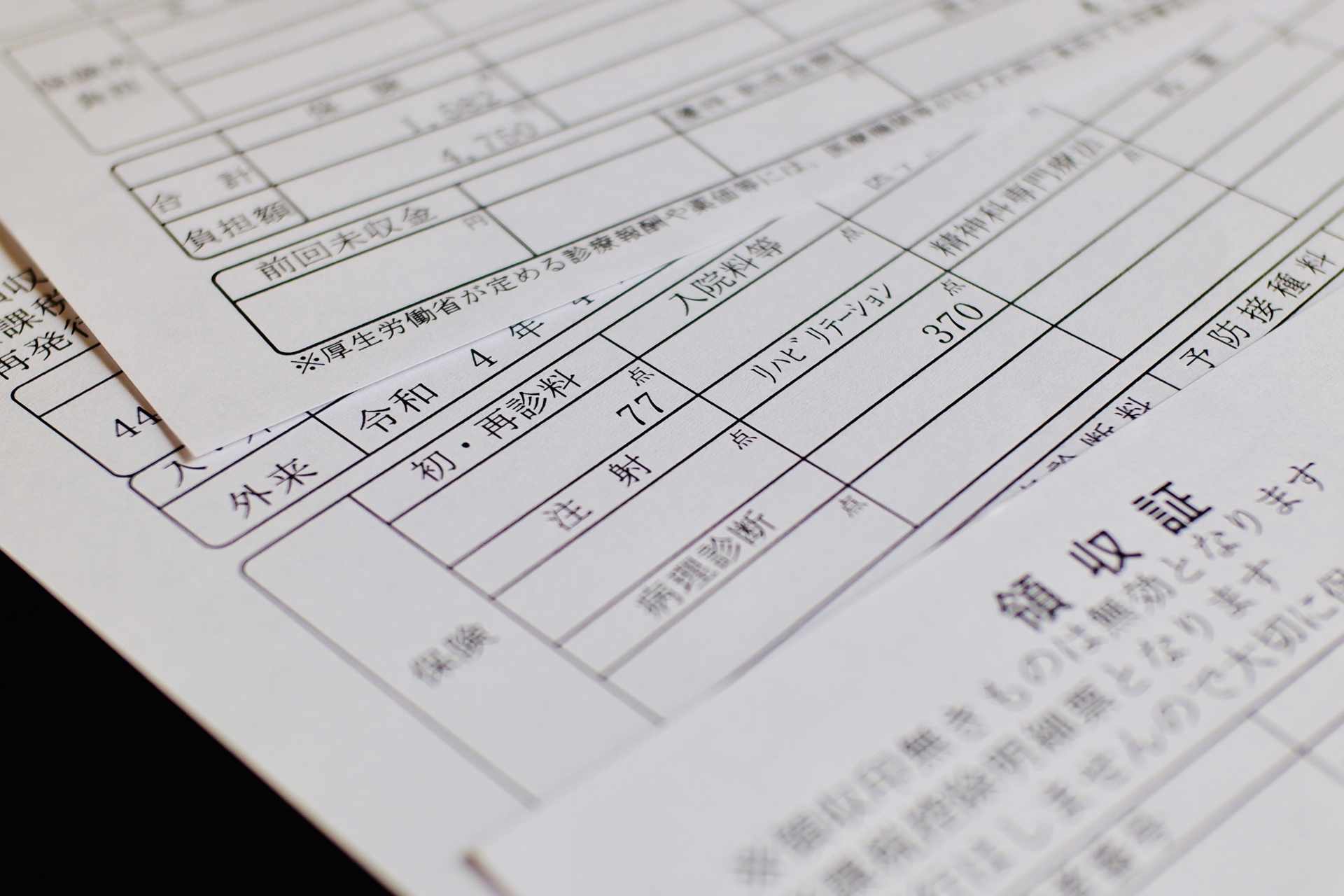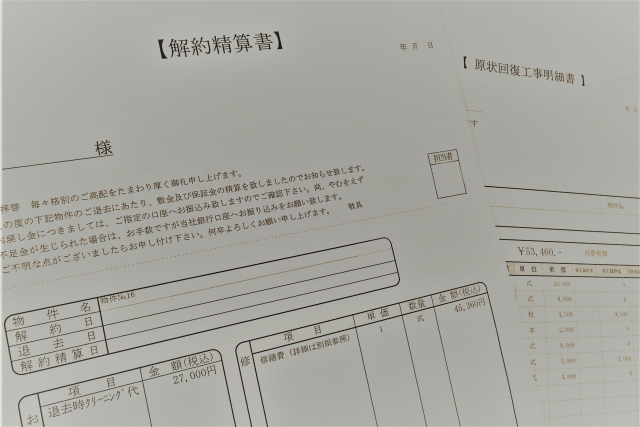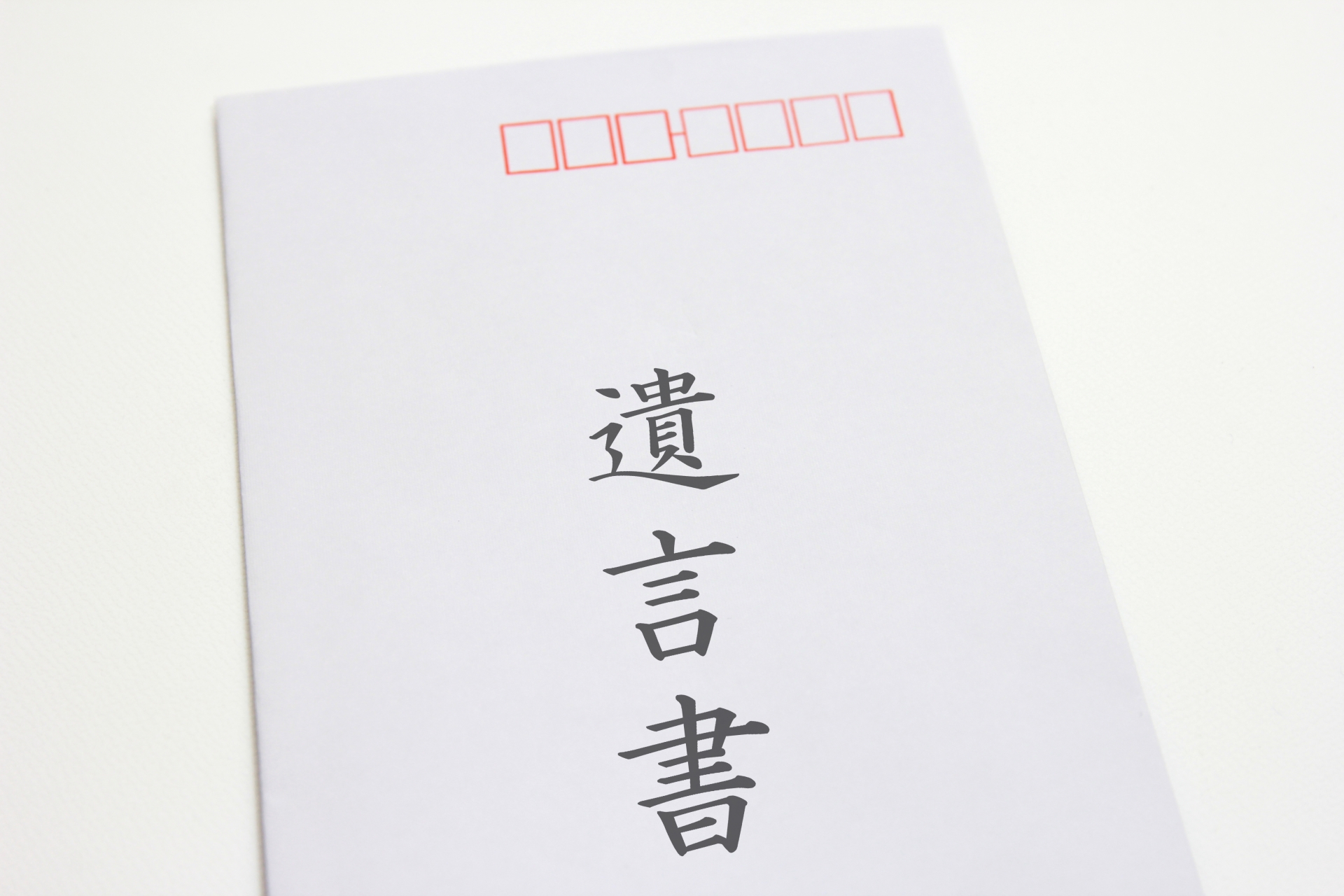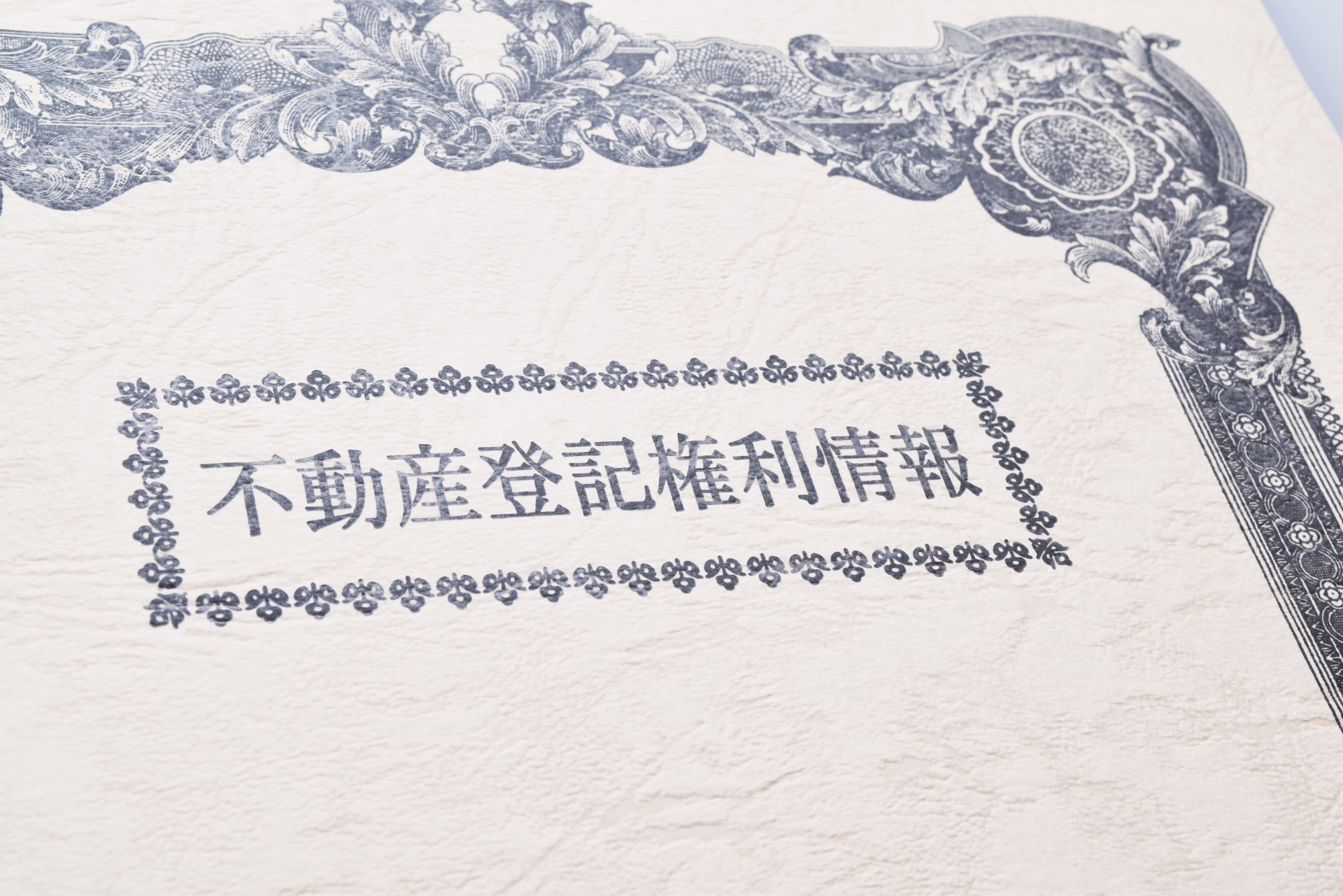お役立ちコラム
お役立ちコラム · 2025/10/17
「親から受け継いだ土地をそのままにしている」
「遠方の実家を空き家のまま、あるいは解体して更地のまま放置している」
「使い道もなく、毎年固定資産税だけ払っている」
そんな悩みを持つ方が、いま全国で増えています。
実は、こうした“ほとんど使われていない土地”を売るとき、税金が安くなる特別な制度があることをご存じでしょうか?
それが今回ご紹介する、「低未利用地の譲渡に関する100万円の特別控除」制度(正式名称:「低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除」)です。
この制度を上手に使えば、
✅ 使っていない土地を手放してスッキリ
✅ 税金の負担も軽くなり
✅ 地域の空き地対策にも貢献
まさに、「持て余していた土地を前向きに整理できる」仕組みです。
では、どんな土地が対象なのか?
どうすれば控除を受けられるのか?
お役立ちコラム · 2025/10/12
「結婚生活を支えてきたけれど、もし将来、別々の道を歩むことになったら…」
「私は扶養内で働いていたけれど、年金ってどうなるんだろう?」
「将来、年金ってどうなるの?」
そんな疑問を持つ方は多いと思います。
とくに、パートや短時間勤務などで家庭と仕事を両立してきた方にとって、
“老後の年金がどれくらいもらえるのか”は、とても気になるテーマです。
実は、結婚しているあいだに夫婦で築いた厚生年金の記録を分けられる制度があるのをご存じですか?
それが「年金分割制度」です。
これは、夫婦が協力して築いた年金記録を、離婚後に公平に分ける仕組み。
家事や育児、パートなど、家庭を支えた時間もきちんと評価してくれる制度なんです。
この制度を知っておくだけで、将来の年金を自分の力で守る第一歩になります。
お役立ちコラム · 2024/11/18
「ふるさと納税」は、人口減少や過疎により税収が減少した地域と、都市部との格差を是正することを目的とした制度で、2008年5月にスタートしました。
昨年度には、寄附金額は1兆1175億円、約1,000万人が利用する制度となっています(住民税を納めている人は全国でおよそ6,000万人で、6人に1人がふるさと納税を利用したことになります)。
なお、寄附先の自治体は、納税者のふるさとに限定されていないため、自分の好きな自治体に寄附ができます。
年末の駆け込みでふるさと納税を考えている方も多いと思います。上手く使えばお得な制度なので、是非使ってみてはいかがでしょうか。
お役立ちコラム · 2024/10/26
共働きのご夫婦の方は、「医療費控除」は夫が申告した方が良いの?妻が申告した方が良いの?夫婦別々で申告した方が良いの?と疑問を持たれてる方が多いと思います。
そもそも医療費控除とはなんぞや?という方もいらっしゃると思います。
まずは、「医療費控除」とはどのような控除かについてみていきましょう。
お役立ちコラム · 2021/01/28
もうすぐ、引っ越しのハイシーズン(だいたい3月・4月頃)といわれる時期がやってきます。
「引っ越し難民」にならないように、進学や就職、転勤などで引っ越しをしなければならない方は、早めに引っ越し業者の確保をしましょう。
そこで引っ越しだけに熱を上げるのではなく、賃貸借契約書の確認も早めに行いましょう。
退去の申し入れは、30日前?、3か月前?。契約書により様々ですが、住宅であれば、30日前や1か月前という記載が多いと思われます。
また、明渡し時の原状回復、敷金の返還等はどうなっているかです。
特に問題となるケースが多いのが、明渡し時の原状回復ではないでしょうか。
お役立ちコラム · 2021/01/16
保証も連帯保証も、いずれも本来の借主(以後「主債務者」)の代わりに借金を支払う(債務を履行する)点では変わりはありません。
但し、保証人は、借主が借金を支払えないときにはじめて責任をます。つまり、二次的な責任を負うのにすぎない。
それに対し、連帯保証人は借主と同じ立場で責任を負います。つまり、一次的な責任を負うことになります。
お役立ちコラム · 2020/03/13
平成30年民法(相続法)改正以前は、自筆証書遺言を作成するときは全文を自書しなければなりませんでした。所有財産が多数ある場合でも財産目録を含めた全文を自書しなければならなかったということです。そうしますと、財産目録を含めた全文自書は相当な労力を要するという問題がありました。
そこで今回の民法(相続法)改正により、自筆証書遺言と一体のものとして相続財産の全部または一部の目録を添付する場合には、その目録についていは自書することを要しないこととしたのです。
お役立ちコラム · 2020/02/21
仕事柄、相続が発生したお客様の遺言書を拝見する機会が多いのですが、遺留分を考慮していない遺言書や表現が曖昧な遺言書が多いため、以下をお読みになって少しでもご参考にしていただければと思います。
お役立ちコラム · 2020/02/07
2020年には、平成30年度の税制改正や働き方改革関連法、平成29年度に成立した債権関係や相続関係の改正民法の一部が施行されます。
主なイベントとそれそれの実施時期を確認しておきましょう。
お役立ちコラム · 2019/07/30
最近、若い買主の方から「所有権移転登記は自分でしたい。売主さんに承諾をとってもらえませか?」という依頼が2回続けてありました。
普通であれば、司法書士にお願いするのですが、費用を抑えたいというのもあるようです。また、勉強熱心なお客様も多く、今後の為に、人任せでなく自分で登記をしたいという方が増えているようです。
但し、登記は、表題部であれば「土地家屋調査士」、権利部であれば「司法書士」という専門家がいるくらい重要なものですので、自信のない方はやはりそのような専門家に依頼した方が無難でしょう。